
「同じ遊びばかりしていたり、急にぐるぐる回ったり…まわりの声が届かないことが増えて心配です」
そんなご相談が届きました。
お子さんが繰り返し同じ行動をする姿に、心配になったことはありませんか?
例えば、手をひらひらさせる、順番に物を並べる、特定の言葉を何度もつぶやく…といった行動は、一見意味がないように見えても、その子にとって大切な理由があることが多いのです。


こうした繰り返しの行動や強いこだわりは、「癖」とは少し違います。
多くの場合、それは気持ちを落ち着けたり、不安を和らげたりするための“自分なりの方法”なのです。
特に、退屈を感じているとき、困っているとき、緊張や不安を抱えているときなど、心の中を整理したい場面でこだわり行動が表れやすくなります。
ですが、それが強く出すぎると、周囲と関わるきっかけが少なくなってしまったり、遊びや日常生活に支障が出ることも。
そういった場合には、「無理にやめさせる」のではなく、「別の方法でも安心できるように導いていく」ことがポイントになります。
お子さんの行動には必ず理由があります。
繰り返しの行動を制限するのではなく、まずはその背景を理解し、「他にも楽しいことがあるよ」と伝えられる関わり方を心がけましょう。
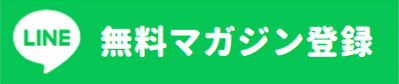
こだわりが強く出ているときは、視野がぐっと狭くなっていることがあります。
だからこそ、今好きなことを出発点にして、少しずつ興味を広げていくのが効果的です。
たとえば…
「こだわりを減らす」のではなく、「こだわりの外にも楽しいことがある」経験を少しずつ増やしていくことで、自然と行動のバリエーションが広がっていきます。
お子さんの行動の中には、ことばには表れないさまざまなサインが含まれています。
その行動が**「どんな場面で起きて」「そのあとにどんな結果が得られているか」を丁寧に観察することで、行動がどうして続いているのか、そしてどこに働きかければよいか**が見えてきます。
これは「応用行動分析(ABA)」の基本的な考え方で、行動を“理由のあるもの”として捉え、観察可能な行動とその前後の環境から関わり方を考える方法です。
むやみに制限するのではなく、行動の背景にある「意図された結果」や「満たされているニーズ」を理解することが、より良いサポートへの第一歩になります。
「うちの子の場合はどこに注目したらいい?」という個別のご相談は、発達相談kikottoで受け付けています。
初回から2週間は無料でご利用いただけますので、ぜひLINEからお気軽にご登録ください。

