
~先生からの相談に、家庭でできるサポートを考える~
「授業中、席を立ってウロウロしてしまいます」と担任の先生から言われ、ちょっと戸惑った…そんなご家庭も少なくないのではないでしょうか?
今回は、そんなお悩みに寄せられたご相談をもとに、「家庭ではどうサポートしていけば良いのか?」を一緒に考えていきます。

お子さんによって背景はさまざまですが、よくある理由としては以下のようなものが考えられます。
特にADHD傾向のあるお子さんは、こうした傾向が強く出ることもありますが、「困った行動」ととらえるよりも、「特性」や「個性」として理解してあげることが、何より大切です。

「座ってて」と口頭で言われてもピンとこない場合があります。視覚的に伝えたり、目を見て短く伝えたり、手順を簡潔にまとめたりすることで、理解しやすくなります。
できたときにはしっかり褒めることもお忘れなく!
座ることをゴールにせず、「座ってできる楽しいこと」「達成感のあること」を用意しましょう。たとえば、ちょっとしたワークや好きな活動があると、「自然と座っている時間」が伸びていくことがあります。
見通しを持てないことで、そわそわしてしまうこともあります。そんなときは…
などの工夫で、不安を和らげることができます。
待つことが苦手なお子さんには、「待っている間にやること」を用意しておくのもおすすめ。たとえば…
ちょっとした工夫が、大きな助けになることがあります。
ゲーム感覚で「お母さんの動きを全部真似してね!」などと遊びながら、周囲をよく見る練習をしてみるのも効果的です。真似っこ遊びは、自然と集団の動きを意識する力にもつながっていきます。
「皆と同じように、お行儀よくすること」が大切だと思ってしまいがちですが、そればかりに気を取られると、お子さんの「得意」や「好き」が埋もれてしまうこともあります。
興味のあることにはとことん集中する能力は、周りのお友達よりも秀でているかもしれません。だからこそ、「何が好きか」「何に夢中になれるか」を大切にし、その子なりの成長を見守る環境を整えていくことが、なにより大切です。
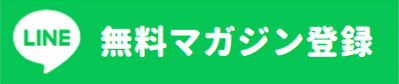
目立つ行動があると、どうしても注意が増えてしまいがちです。でも、何度も注意されることで、「自分はダメなんだ」と自信を失ってしまうお子さんも少なくありません。
できることに目を向け、「ここができたね」「今はがんばってたね」と声をかけてあげることで、お子さんの自己肯定感はぐっと育っていきます。
個別面談のときなどに「うちの子、待ってる間に困っていることがあるみたいで…」と、やんわり伝えるのも◎。「待ち時間にやっていい課題を用意してもいいですか?」と相談してみるのもよいかもしれません。
お子さんが授業中に立ち歩いてしまうことも、何かしらの「理由」や「背景」があるもの。周りの大人が少し見方を変えることで、お子さんの過ごしやすさも大きく変わっていきます。
もし「うちの子も当てはまるかも…」と感じたら、ぜひ気軽にご相談ください。
個別のご相談は【kikotto】で受け付けています。LINEに登録していただくと、2週間は無料で相談できますよ。


過去にも似たようなご相談が寄せられています。以下の記事もぜひ参考にしてみてください。