
最近、こんなご相談をいただきました。
「担任の先生から“授業中にうろうろ歩いてしまう”と聞きました。叱っても改善せず、どう関わっていけばいいのか悩んでいます」
授業中に突然立ち歩いたり、注意をしても繰り返してしまったり…こうした行動の背景には、感覚の感じ方に偏り(=感覚の敏感さや鈍さ)が関係していることもあります。


例えば、お子さんがじっとしていられず動いてしまうのは、「動いていないと落ち着かない」「何かを触っていないと不安」といった感覚的な不安定さから来ていることがあります。
服を引っ張る、口に入れる、字が極端に濃い・薄いなどの行動も、感覚の受け取り方が関係しているかもしれません。
♦️ 小さな手遊び道具を活用する
→ ハンドスピナーやスクイーズ、チューイングネックレスなどで、触りたい・噛みたい欲求を安全に満たせます。
♦️ 手指の筋トレをしてみよう
→ 粘土遊びや握力ボールなどで指の力を育てると、書く時の力加減が上手になります。
♦️ 行動を具体的に伝える
→ 「レジではカートを持って静かに立とうね」など、イメージしやすく伝えるのがポイントです。
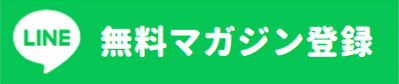
□ 注目しているときに、短く指示を出す
→ 肩を軽くトントンするなどしてから「短く」「わかりやすく」伝えると届きやすくなります。
□ 「ダメ!」ではなく「こうしてほしい」を伝える
→ 例:「走らない!」より「歩こうね」と言い換えて。視覚的なカードも効果的です。
□ 「じっとできる」場面をスモールステップで増やす
→ 例えば、「エレベーターでは足を床につけて、ママと手をつなぐ」など短い場面からスタート。
大きな声を出す、動き回る、話を聞いていないように見える…
そんな行動の裏には、「困った子」ではなく「困っている子」のサインが隠れているかもしれません。
📩 今、お子さんの行動で気になることがあれば、ぜひ一度ご相談ください。
LINEでkikottoに登録すると、2週間無料で個別相談が可能です!

