
最近、こんなご相談をいただきました。
「うちの子、ごはんやおかずを手で触ったり、指でつついて遊んでしまうんです…。」
食べ物に興味があるのはいいことですが、どうしたらいいのか対応に悩んでしまいますよね。
お子さんが食事中に手を伸ばして、ぷにぷにごはんをつついたり、触って感触を楽しんでいる…。
多くのご家庭で一度は経験する「あるある」の行動だと思います。


こうした行動、実は「食べること」や「食べ物」への興味が芽生えてきたサインであることが多いんです。
特にお肉や白ごはんのように、やわらかくて触感がおもしろいものは、お子さんにとって“ちょっとしたおもちゃ”のような存在に感じられることも。
「これはなに?」「どんな感じ?」と、“知りたい”気持ちがつい手に出てしまっているんですね。
熱い・冷たいなどの温度を確かめたくて触っている場合もありますし、見た目だけではわからないものを、触って確かめようとしているケースもあります
とはいえ、遊びながらの食事が習慣になってしまうと困りますよね。
そんな時は、まず環境をちょっとだけ整えてみましょう。
🔹パーテーションを使ってみる
大人のお皿に持ってあるご飯を触ってしまう、大皿の料理をつついてしまう・・・
そんな時には、100円ショップで買えるアクリル板、ワイヤーネット、フォトフレーム、プラスチックダンボールなどに脚をつけて、お子さんの手が届きづらいように仕切りをつくる。これだけでも「つい手が出る」ことを防げることがあります。
🔹食器の配置を入れ替える
例えば、おにぎりや果物などの固形物など“食べやすく、触ってもまあ大丈夫な”ものをお子さん側に、汁物やタレのついたお肉、飲み物など“熱かったり、触られると困るもの”を大人側に置くと、手を出しにくくなります。
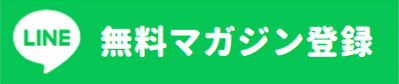
お子さんの“触って知りたい”気持ちには、言葉でイメージさせてあげる方法もあります。
「お母さんが作ったふわふわ卵焼きだよ。あっついから気をつけてね。」
「今日のごはんはつやつやしてるね。やわらかいからお箸で食べようか!」
こんな風に、五感に訴える言葉で伝えることで、触らなくても“なんとなくわかった気がする”感覚を持たせることができます。
触る行動から注意をそらすために、「大きなお口で一緒に食べてみよう!」と声をかけたり、「もぐもぐ~」と表情や音で楽しさを共有するのもおすすめ。
“食べる”こと自体が面白い遊びになれば、自然と手が伸びる行動も減っていきますよ。
お子さんの行動には必ず「意味」や「理由」があります。
ごはんを触ることも、「今、その子にとって必要な経験の一つ」かもしれません。
無理にやめさせるのではなく、一時的に環境を整えたり、言葉で安心感を与えたりしながら、その好奇心をうまく育てていけると良いですね。
「うちの子の場合はどうしたら?」
そんなピンポイントのお悩みは、【kikotto(きこっと)】でお気軽にご相談ください。
今なら2週間無料で相談可能!LINEに登録して、気軽に聞いてみてくださいね👇

