
先日、「特定の音やにおい、人混みが苦手で、お子さんが逃げ出してしまう。どう接したらいいかわからない」というご相談をいただきました。実は、このような「感覚の敏感さや鈍さ」は珍しいことではありません。誰しも少なからず持っていて、大人も無意識のうちに調整しながら生活しているのです。
ただし、お子さんの場合はそれが強く表れると、日常生活や学校生活で困りごとにつながることがあります。ここでは、感覚に敏感なお子さんへの対応について、具体的な工夫をご紹介します。


もしすでに困るようなトラブルが出ている場合は、まず「刺激を減らす」ことが第一歩です。
それでも避けられないときは、
といった工夫で心の準備を整えることが効果的です。
また、小さな成功体験を積み重ねるのも大切。
例えば「時計の音」なら小さい音の時計から慣れていき、少しずつ大きな音に挑戦する。食べ物なら「苦手なキュウリ」から一気に克服するのではなく、似た食材や好みの味付けを探して広げていく。そんなステップが役立ちます。
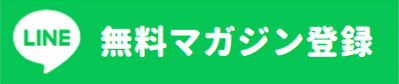
「人が多い場所から逃げ出す」「初めての食べ物を警戒する」といった行動は、お子さんにとっては“自分を守る手段”です。その気持ちに寄り添いながら、少しずつ安心できる環境を広げていくのがポイントです。
例えば、
など、無理のない範囲で“挑戦と成功”を積み重ねることが自信につながります。
一見「感覚の過敏さ」に見えても、実は別の理由で行動している場合もあります。たとえば「うるさい!」と耳をふさぐのが、実は“注目を集めたいサイン”であることも。その場合は、感覚対策とは別のアプローチが必要になります。
感覚の敏感さや鈍さは「個性」のひとつです。無理に克服させるのではなく、お子さんが安心して挑戦できる環境を整えてあげることが大切。少しずつ「できること」を広げていく過程そのものが、成長の力になります。
もし同じようなお悩みがあれば、ぜひ一度ご相談ください。kikottoでは、専門スタッフが一緒に解決の糸口を探します。今なら 2週間無料で相談できますので、LINE登録からお気軽にどうぞ。

