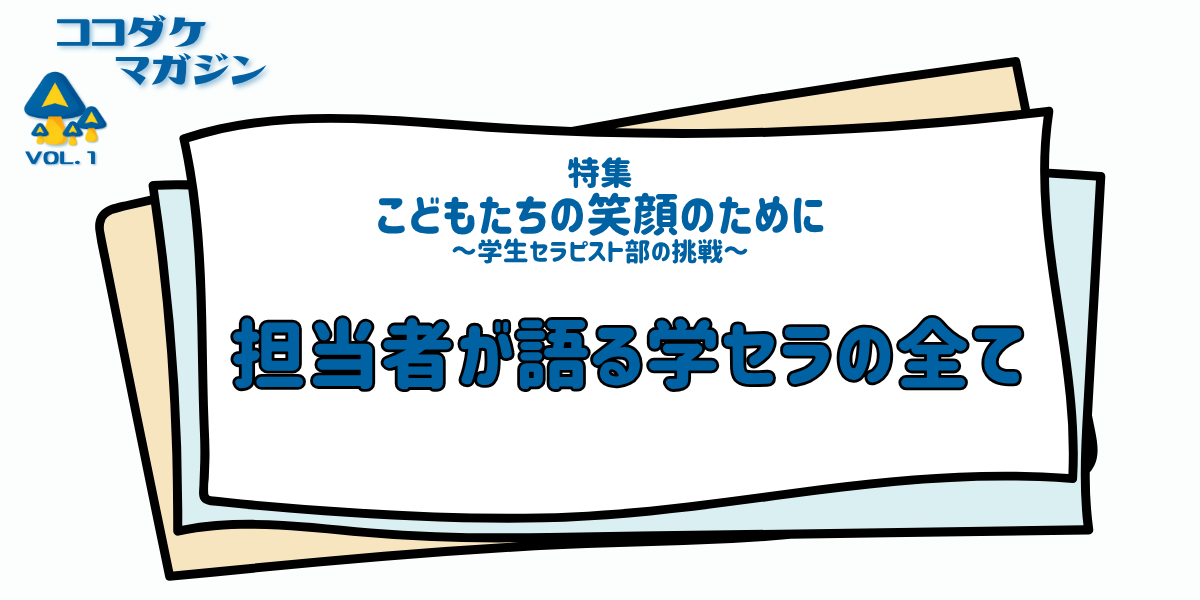
学生たちがセラピストとして学び、成長し、社会に貢献する――ADDS「学生セラピスト部」の取り組みとは
発達に特性を持つ子どもたちの支援を行っている特定非営利活動法人ADDS。その中で、学生たちが実際にセラピストとして活動する「学生セラピスト部」は、単なる学びの場にとどまらず、社会的な影響力を持つ大切な役割を果たしています。学生たちは、現場での実践を通じて専門的な知識を深めるだけでなく、子どもたち一人ひとりの成長に寄り添いながら、自身の成長にも繋げています。
今回のインタビューでは、学生セラピスト部の設立背景やその目的、部の活動がどのように社会に波及しているのか、ADDSならではの支援の特徴、そして学生たちにとっての学びや成長について担当者にお話を伺いました。また、運営における大切にしている価値観や今後のチャレンジ、さらには支援を受ける家族や子どもたちからの反応まで、さまざまな視点から「学生セラピスト部」の活動について深く掘り下げていきます。
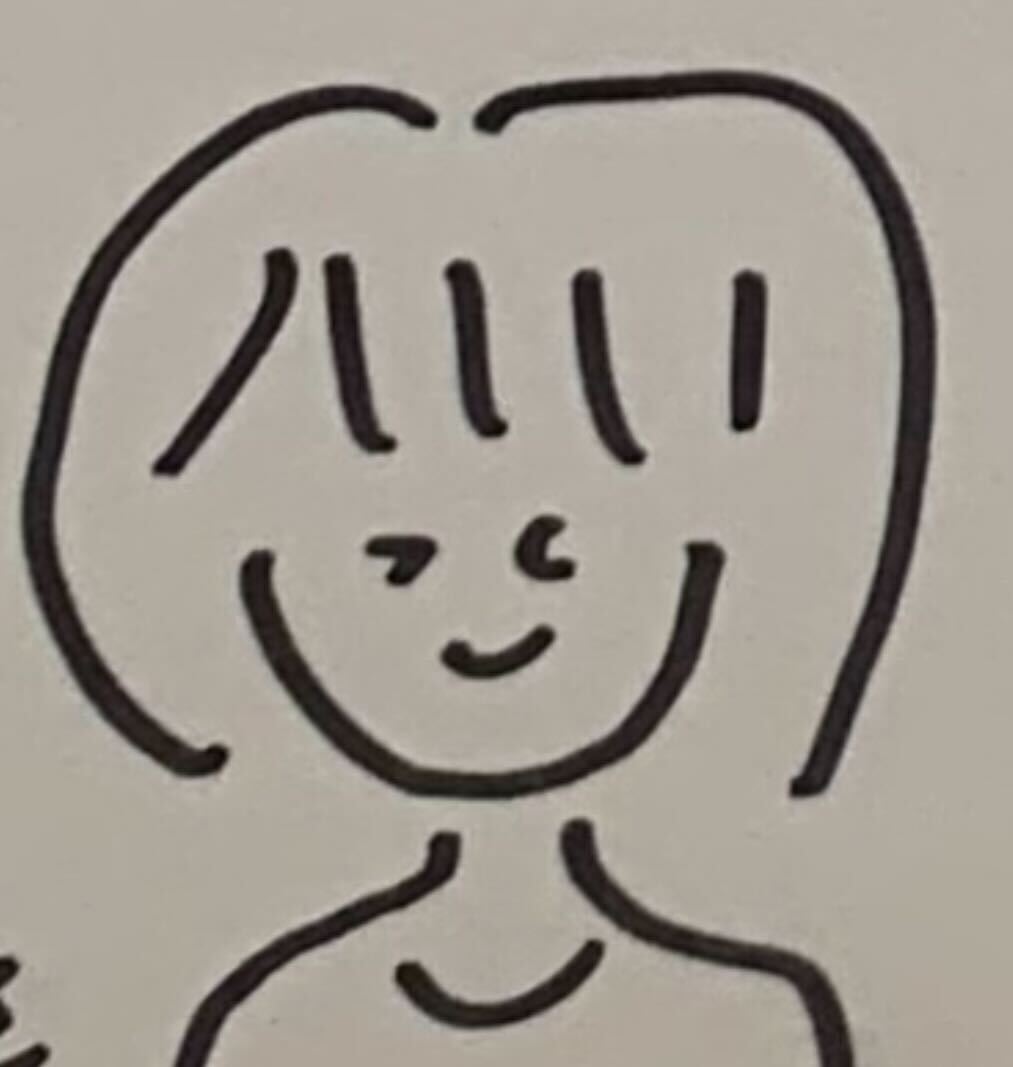
三谷 美薫(みたに みゆき)
元学生セラピスト/ 現ADDS 学生部担当 / 保育士 / ぺあすく(ペアレントトレーニング付きプログラム)や学びの広場(個別支援)で直接支援も行っています。
Q1. 学生セラピスト部を設立された背景や目的について教えてください。
学生セラピストは、ADDSの支援モデルを形作るうえで、創設当初から欠かせない存在でした。ADDSの立ち上げと同時に、「学生セラピスト部」も発足しています。「専門家だけが専門性を抱え込む社会」では、多くの子どもたちに十分な支援が届きません。だからこそ、専門家でも保護者でもない「非専門家」をどう巻き込んでいくかが、子どもたちの環境をより良くしていくための大切な視点だと考えています。
この考えに共感してくれた発達支援に関心のある学生たちが集まり、研修を受け、現場で実際に支援に関わる──
そんな取り組みが、ADDSの活動の原点となっています。
Q2.学生がセラピストとして活動する意義を、どのようにお考えですか?
職員になった今では、学生が社会人として世の中に出る前に、人には人の学び方があることや成長できることをセラピストの活動やボランティア活動を通じて知ることに大きな意義があると思っています。 学生目線では、心理の領域で何か行動したいと思った時に、それが環境的に可能であるというのは救いだったなと思います。心理職は、大学院卒で資格を得てから働くことが一般的ですが、ADDSでは学部生でも、面接と研修、細やかな基準のある試験に合格すれば、セラピストとして勤務することができます。そのため、学部生で学んだことを実践に生かせる機会がある学生部は貴重な場になっていると思います。入ってからプロにする心意気と、それを実現できる制度があることが、ADDSの強みだと思います。
Q3.部の活動を通じて、社会に与えている影響や波及効果はどのようなものだと感じていますか?
ADDS学生部が社会に存在すること自体が、社会に影響を与えていると思います。学生部に入る前に、発達や心理について漠然と興味があり、なんとなく調べている中で、お子さんに重度の知的障害のあるお母さまの「子どもより親の方が先にこの世からいなくなるのだから、自分たちよりも年下の若い人が福祉や教育に興味があるということが本当に嬉しい」というような言葉を見かけて、誰かの興味や好きが、誰かの喜びに繋がることがあるんだ、と印象に残っています。その意味でも、学生部の存在は、そういったご家族の光になるのではないかなと思います。時代や世の中の流れが大きく変わっても、こうしてかつての学生部員と同じように、想いのある学生が存在することそのものが、社会の希望だと思います。 “あなたは社会の希望”という言葉は、実はADDSに入ってから、上司に何度か贈っていただいた言葉の一つなんですが、私からもいまの学生に贈りたい言葉です。
Q4.ADDSならではの支援の特徴や、他団体との差別化ポイントは何でしょうか?
やはり、エビデンスに基づいてかつきめ細やかに体系化された支援を提供しているという点が特徴でしょうか。また、診断の有無やその名称などに関わらず、”目のまえのお子さんにとって必要なことは何か”を日々追求しながら、セラピーをしていることも大切にしているポイントかなと思います。
Q5.学生にとって、この部での経験がどのような学びや成長につながっていると感じますか?
学生部では、いま自分たちが学生部として出来ることは何かを、みんなで常々考えています。 はじめは対自分たち、対お子さんに向けてだけだった視点が、対ご家族、対仲間へと広がっているのを感じます。 そんな姿を見ていると、学生部の活動を通して学生は、「目の前の人に、その時の自分に何ができるか」を考えて実行する力を獲得しているのかなと思います。
Q6.運営にあたって特に大切にしている価値観やビジョンがあれば教えてください。
学生が楽しく有意義な時間を過ごすこと!に、特に価値を置いています。 学生って、大学の授業は当たり前にありますし、そこに実習やアルバイト、お家のことなどが加わって本当に忙しいと思います。 そんな中で、交通費や活動費を自費で出してまでも来てくれているのだから、有意義な時間を過ごしてもらいたいと心から思っています。 お子さんをお預かりするイベントの時は、もちろんお子さんやご家族の皆さまの笑顔を引き出せているかなどを気にかけて運営していますが、学生が自然に笑えているかという点も大切にしていて。 笑顔の量は、学生からスタッフへのフィードバックとして受け取っています。
Q7.今後の目標や、部として取り組んでいきたい新たなチャレンジはありますか?
目下の目標は、部員を増やすことです!!! いまは人数が少なくなってきて、小さくまとまっている感じですが、部員を増やしてもっと輪を広げたいなというのが担当者の想いです。人が少なくても想いは共有できるし運営もできますが、もっと多くの活動を、より多くの学生やお子さん、ご家族に届けられたらいいなと思っています。
Q8.支援を受けるご家族・子どもたちからの反応や、印象的な声があれば教えてください。
個人的なことで恐縮ですが、学生時代に訪問セラピーをさせていただいていたご家庭のお母さまに、 「わたしは三谷先生のファンなんです」と言っていただいたことは、当時から今でも、お守りになっています。 お子さんで言うと、担当当初は手を持ってひらがなを一緒になぞる練習をしていたお子さんが、卒業時にお手紙をくださって、お母さまからは「1人で書きました」の一言が。その一生懸命な筆跡に、私も感涙でした。 そんな、何にも代え難い、ご家族の皆さまやお子さんから日々いただくパワーを糧に、セラピストもまた一歩、進めるんじゃないかと思っています。 いつもありがとうございます。
Q9.部の強みをさらに活かすために、今後どのような仕組みやサポートを強化したいと考えていますか?
今の学生部は、雰囲気がすごくいいのと、自走するチームになってきているのが強みだなと思っています。 視座も高くいろんなことが見えるようになっていますが、それに対して活動の場や機会が少なかったり、活動内容が固定化していることがもどかしいです。今後は、学生部の活動機会や幅、学びの場を増やしていくため、まずはスタッフ主導で新たな機会づくりを強化しながら、徐々に学生による運営へと移行できたらいいなと思います。
Q10.学生セラピスト部の活動を社会に広めていく上で、どんな協力や連携を求めていますか?
学生部を社会に広めていくうえで、地域や外部コミュニティとの連携は欠かせないのではないかと思っています。先述した通り、いまは人数が少ないこともあって活動の幅が狭まっていて、なかなか学生部の魅力をアピールできていないもどかしさがあります。もちろんこちらから動いていく所存ではありますが、機会の提供やサポートで引き続き伴走していただけると幸いです。これまでの学生達が資金を出して活動するという運営形態から、皆様のご寄付を活用する形態にシフトをしますが、そんな中でもなるべく予算をかけずにやりくりしていきたいと思っておりますので、工作に使用する文具や、お子さんをお預かりする際に必要となる場所としてのレンタルスペースの提供等にご縁を頂けましたら、担当者としましても嬉しい限りです。
この記事はADDSにご寄付してくださっている方、過去にご寄付をしてくださった方を対象にお送りしている活動報告メール「ココダケマガジン VOL. 1」のために作成されました。





 top
top